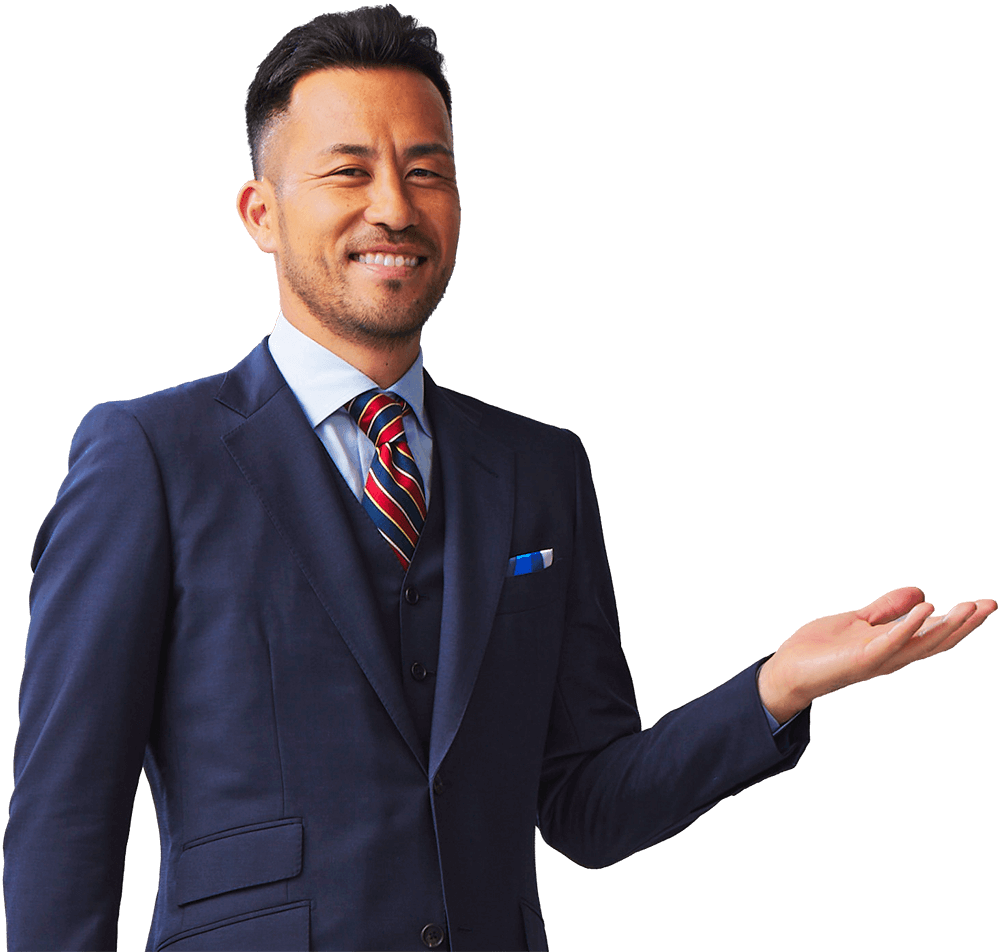BtoBtoCで事業を営むメーカーのマーケターにとって、接点が限られるなかでの顧客理解は大きな課題だ。「私たちは情報取得において弱者だ」と自認するアサヒビールの小野寺慶祐氏もそのひとり。しかし、同社はその壁を破り、LINE公式アカウントとTreasure Data CDPを軸にした独自のデータ活用で、着実に成果を上げている。
外部メディア、飲食や小売との連携まで、幅広い施策に取り組むアサヒビールの試行錯誤は、データを活用したマーケティングの示唆に満ちている。特に、ファーストパーティデータの取得と活用に苦慮するメーカーの方は、ぜひ参考にしていただきたい。

小野寺 慶祐氏
飲用にとどまらずトータルの顧客体験を充実させる
アサヒビールは、ロングセラーの「スーパードライ」、RTD(Ready to Drink、フタを開けてすぐ飲める飲料)の常識を変えた「未来のレモンサワー」などを製造・販売するアルコール飲料メーカー。ビール、発泡酒、チューハイ、ワイン、ウイスキー、さらにノンアルコール飲料と、幅広いカテゴリーを展開する。
親会社のアサヒグループホールディングスは、「期待を超えるおいしさ、楽しい生活文化の創造」をミッションとし、アサヒビール単体でも「すべてのお客さまに、最高の明日を。」のビジョンを掲げる。「商品を通して、おいしい+アルファの価値を創出する」と、自社のビジネスを表現する小野寺氏。飲用時はもちろん、各種メディアやメッセージアプリ、キャンペーンやイベントなど、コミュニケーションを通したトータルの顧客体験を、極めて重視している。
一方で、小売店や飲食店を介して商品を販売するBtoBtoCのビジネスであり、顧客との直接的な接点は限られる。メーカー独特のコミュニケーションの課題を解決するため、2024年にメディア広告などを担う宣伝部と、CRM推進を担うデジタルマーケティング部を統合。コミュニケーションデザイン部を新設した。
狙いは、特徴の異なるデータを収集、活用しながら、フルファネルで一貫性のあるコミュニケーションを可能にすることだ。旧宣伝部が扱っていたメディア広告では、消費者に広くアプローチし認知や興味を喚起できる。活用する媒体社のセカンドパーティデータは多岐にわたる反面、酒類に関するデータは「『お酒に興味がある』いった粒度の大きいセグメント」(小野寺氏)で集計されていることが多く、最近は購買データと連携したターゲティングも可能になりつつあるものの、ピンポイントのターゲティングは難しい。
旧デジタルマーケティング部では、飲用ブランドなど詳細なファーストパーティデータを収集し、精度の高いCRMを行ってきた。購買や継続など行動につながるコミュニケーションが可能だが、前述のようにメーカーという立場上、データの獲得機会は限られる。
部門の統合で両者のデータを連携することで、よりシームレスなデータ活用と顧客体験を実現できるというわけだ。
LINE公式アカウントで顧客データを収集
長い時間をかけて収集したファーストパーティデータは、他社にない資産だ。同社はLINEとTreasure Data CDPを中心に、その活用に取り組んでいる。
前者の仕組みはごくシンプルだ。アサヒビールのLINE公式アカウントに友だち登録してもらい、個人名を特定せずID単位でデータを管理する。そのうえで、アンケートや配信コンテンツの閲覧履歴などから、顧客理解を深めていく。
IDの収集は、商品やアイテムのプレゼントキャンペーン、ライブや試飲イベントなど、オフライン/オンラインの施策で行った。2025年4月現在、友だち登録は2000万を超えている。
特に重視しているのは、飲用ブランドの把握だ。「例えば、スーパードライの購入が条件のキャンペーンに参加したお客様は、日頃から飲んでいただいていることがわかる。定期的なチャットアンケートで、日頃飲んでいるブランドを聞くこともできる。すべてをLINEのプラットフォームに集約することで、お客様の解像度がどんどん上がっていった。同じツールの中で、コンテンツ配信など、コミュニケーションを完結できるのも良い」(小野寺氏)
アルコールの飲用ブランドがわかるのは、マーケティングの大きなメリットだ。ブランドスイッチを促すこともあるか? 小野寺氏に尋ねると、「スイッチという考え方は、少し企業目線に偏っている。多様な飲用体験を楽しむなかで、選択肢としてアサヒビールのブランドも試していただければ良い」と、あくまで顧客体験重視のスタンスで回答した。
ファーストパーティデータをCDPに統合し広告に活用
こうして充実させた顧客情報のすべてを、LINEのツール上で管理することはできない。アサヒビールでは、収集した多様なデータをTreasure Data CDPに格納し、LINE IDにひも付けて運用している。
成功事例のひとつが、24年9月に実施した缶チューハイ「アサヒ贅沢搾り」のプレゼントキャンペーンだ。「アサヒ贅沢搾り」を飲用していると回答し、かつ同社のLINE公式アカウントに対して接触頻度の高いIDを、Treasure Data CDPで抽出。LINEヤフーの広告プラットフォーム上で活用した。
ひとつのLINE IDには、「Yahoo! JAPAN」「Yahoo!ショッピング」「LINE NEWS」などでの検索、購買、閲覧の行動データ(LINEヤフーのセカンドパーティデータ)と、上記のファーストパーティデータがひも付いている。広告プラットフォーム上でこれらを突合し、さらに類似拡張をかけると、「アサヒ贅沢搾り」のユーザーに傾向の近いセグメントを作成できる。
ここにターゲティング広告を配信すると、媒体社のセカンドパーティデータだけでつくったセグメントと比較して、ROIは2.7倍まで向上した。
「商品に興味を持つお客様を目的変数、媒体上の属性・行動データを説明変数とすることで、潜在的なお客様を掘り起こせる。自社データの強みと弱み、媒体を利用するメリットを理解すれば、様々なやり方があると気付いた」(小野寺氏)
アサヒビールは、自社の領域であるアルコールに関して、顧客の理解を高めていた。媒体社はライフスタイル上の様々な角度から、ユーザーをとらえている。両方のデータを合わせることで、より鮮明で包括的な顧客像に対して、コミュニケーションできるようになったのだ。
翻って、広告プラットフォームのデータで、自社のCRMを改善することもできる。
例えば、スーパードライのキャンペーン広告から、LINE公式アカウントに友だち登録した顧客に対して、缶チューハイのコンテンツを配信すると、的外れになりかねない。あるいは以前キャンペーンに参加したのに、次回の案内がなければ、顧客をがっかりさせてしまう可能性もある。
流入経路とコンテンツを連動させ、上記のような不一致を解消することで、コミュニケーションに一貫性が生まれる。「当たり前のことができていなかった」と小野寺氏が語るように、サイロ化された組織、データ管理のなかでは、簡単にみえる連携が難しいケースもある。あらゆる顧客情報を統合するCDPが、必要とされる所以だ。
飲食、小売店との連携に厚みを増すデータ活用
広告/CRMの統合に続いて、小野寺氏は飲食店との連携に話題を広げた。前述の通り、アサヒビールの主な販売経路は、小売店と飲食店のふたつ。売上としては小売の比率が高いものの、体験の提供という点では、飲食店の果たす役割は大きい。
そんな同社の認識がよく現れているのが、2025年1月に開始したスーパードライの飲用品質を向上する飲食店認定制度「スーパーコールド認定店」だ。スーパードライの最大の特徴である「辛口」をより一層引き立てるビールの「冷え」に着目。ビールの温度を「4℃未満」で提供するよう飲食店に協力を促し、温度を含めた複数の品質管理基準を満たす店舗を認定するのだ。
飲食店でキンキンに冷えたスーパードライを体験した人が、ブランドのファンになる可能性はある。ただ、「たまたま入った飲食店で飲んでくださった段階で、”ブランドのユーザー”と定義するのはまだ早い」と、小野寺氏は言う。
キャンペーン申し込みや(過去には缶ビールの無料クーポンプレゼントを実施)、割引クーポンの利用など、LINEを経由して、スーパーコールドの体験をしたことは把握できるが、それが「顧客自身の能動的な行動だったか」までは不明だ。
しかし、その後もLINEでつながり、コンテンツ配信して、スーパードライの魅力を伝えることはできる。例えば、春先の気温が高い日にビールを勧められれば、顧客のなかで、飲食店で飲んだキンキンのスーパードライが想起されるだろう。
こうした一連の体験を経て、アンケートでスーパードライを飲用銘柄に選択したり、キャンペーンに参加する可能性はぐっと高まる。ここまでくれば、本当のファンと言ってよいだろう。「おいしかったビールの思い出を、コミュニケーションで蘇らせることができれば、お客様の幸せにもつながる」と小野寺氏は語る。
また、メーカーと小売店、飲食店は、顧客を共有する関係でもある。LINEの接点とCDPの顧客情報を持つアサヒビールは、顧客に合ったブランドの情報を発信し店舗への来店を促すなど、共同プロモーションの企画も可能だ。
CDPの機械学習でファーストパーティデータのさらなる活用を
アサヒビールの事例は、直接的な顧客接点が限られていても、外部のデータや間接的な接点を組み合わせることで、広範なマーケティングが可能なことを示している。データを統合する基盤としてTreasure Data CDPを利用し、マーケターの仮説に基づく施策を行ってきたわけだが、小野寺氏は機械学習の可能性も示唆する。
過去のキャンペーンに参加したIDを目的変数とし、コンテンツへのレスポンスなどの行動データやアンケートの回答データなどを、説明変数として設定する。これを機械学習にかけ、類似した傾向をスコア化し、キャンペーンに参加可能性の高いIDを抽出する、という流れだ。
アサヒビールは、この方法でいくつかのセグメントを作成し、LINEでコンテンツを配信した。結果、スコアの高いセグメントほど、高いコンバージョンレートを得たという。
「顧客データのなかには、人間の頭では理解できないものも含め、その人を説明するさまざまな要素が詰まっている。機械学習を活用することで、より深くデータを使い切れると実感している」(小野寺氏)。

小野寺 慶祐氏
CDPをデータクリーンルームのハブに
ファーストパーティデータとセカンドパーティデータのかけ合わせ、という点で、小野寺氏が次に見据えるのがデータクリーンルームの活用だ。Cookieに依存することなく、個人情報を保護しながら、広告プラットフォームなどの顧客データを精緻に分析できる。
ここで重要なのが、実務上の効率だという。データクリーンルームは、メディアをはじめ、データを保有するプラットフォーマーが提供しているが、当然ながら、それぞれに特性は異なる。広告主は複数のデータクリーンルームを、独自データも合わせて有効活用したいが、そのための管理コストは小さくない。
そこで小野寺氏は「Treasure Data CDPから、各データクリーンルームへ接続できるようになれば…」と期待を寄せる。例えば、LINEヤフーとトレジャーデータが開発したデータクリーンルームでは、CDPに格納したファーストパーティデータと、LINEやYahoo!などのセカンドパーティデータを、比較的容易に突合できる。同じような仕組みが各プラットフォーマーと構築していけば、小野寺氏の言う世界に近づくだろう。
各種マーケティングツールとの豊富なコネクタは、Treasure Data CDPの大きな特徴。今後活用が広がるデータクリーンルームに対しても、ハブとして機能できるよう連携を進めていきたい。