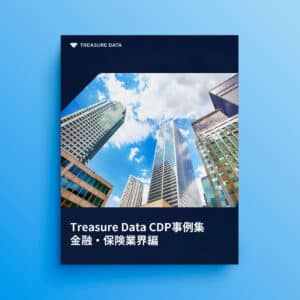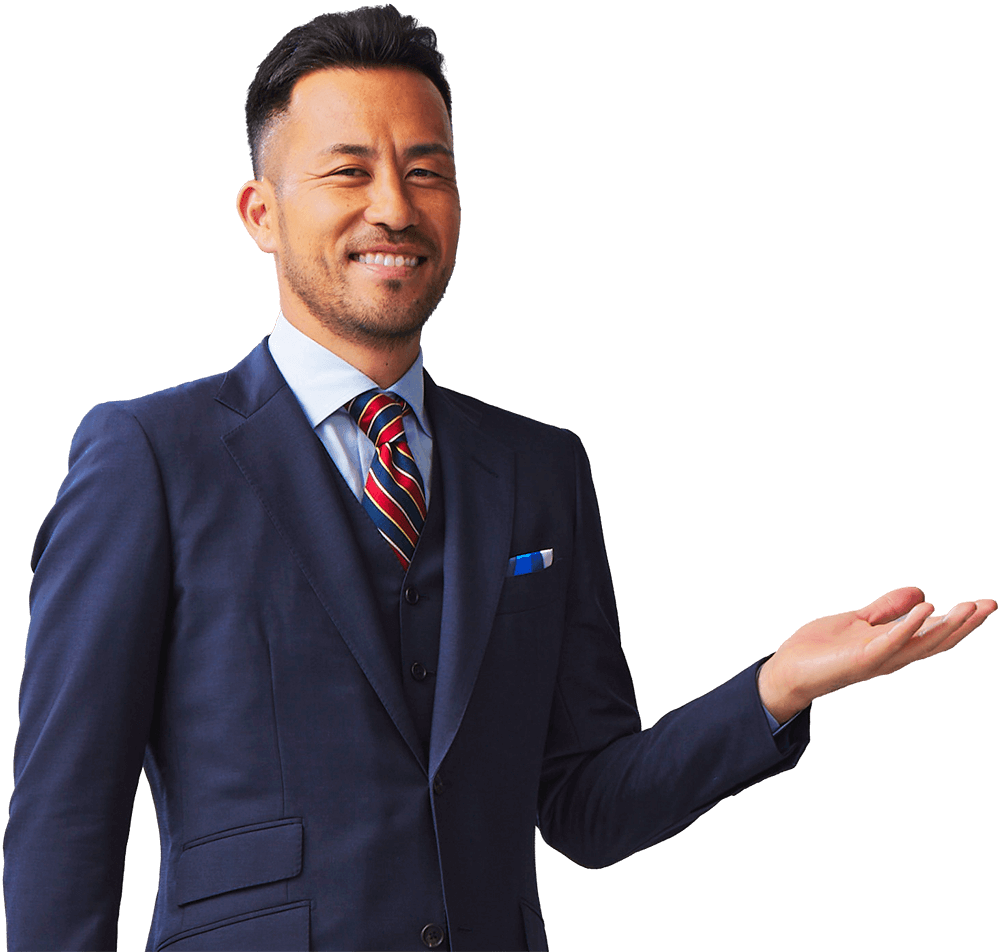「Insurhealth®(インシュアヘルス)」というユニークなコンセプトを掲げ、保険ビジネスの革新に挑むSOMPOひまわり生命保険。これまで以上に顧客との親密なコミュニケーションが求められるなかで、多様な接点から得られる顧客データと、それらを統合するTreasure Data CDPが大きな役割を果たしている。最前線で顧客データの活用を担い、従来にない顧客コミュニケーションに取り組む山下陽氏、髙橋基氏に、「インシュアヘルス」の推進と、CDP活用の現在地を聞いた。
新しい保険の考え方「インシュアヘルス」とは
「Insurhealth®(インシュアヘルス)」とは、保険本来の役割 (Insurance)と健康をサポートする機能(Healthcare)を組み合わせた新しい価値である。万が一を保障するだけではなく、万が一を可能な限りなくしていくことに挑戦している。
加入者全員が一定の保険料を負担し、病気やケガ、事故などの際に給付を受けるという基本的な仕組みは、保険業各社とも変わらない。また、保険会社は認可制で、極端なサービスはできない上に、よい商品は他社に模倣されやすい。基本的に差別化が難しいビジネスモデルといえる。
そのような中、同社は、伝統的な生命保険会社の枠組みを脱し、国民の健康を応援する「健康応援企業」へのさらなる進化を目指している。「インシュアヘルス」はその中核をなすコンセプトであり、「健康☆チャレンジ!制度」など、加入者の健康をサポートするサービスが人気を集める。インシュアヘルス商品は2018年の販売開始以降、累計販売件数は200万件に達し(2025年3月時点)、多くのお客さまに共感いただいている。
「健康☆チャレンジ!制度」は、加入者が契約後2〜5年の間に、喫煙状況、健康状態を改善すると、保険料が割安となり、さらに契約日にさかのぼって計算した保険料差額相当額を「健康チャレンジ祝金」として受け取れるサービス。わかりやすいインセンティブを提供し、加入者が積極的・能動的に健康行動へ取り組むことを促す狙いだ。
2024年には、将来の健康リスクを予測するとともに、健康リスクの回避を支援するアプリ「MYひまわり」をリリースした。健康診断結果をカメラ撮影するだけで、数値等の結果を整理して保存が可能。5年以内に異常値になる可能性が高い検査項目を、AIが独自で判定、さらにユーザーにおすすめの健康行動を提案してくれる。

このように、SOMPOひまわり生命保険は、着実に「インシュアヘルス」の取り組みを充実させている。だが、健康は万人に共通の価値であり、医療や製薬、スポーツ、食品、ITなど、ヘルスケアサービスを提供する事業者は数しれない。そのなかで、保険会社だからこそ提供できる価値とは何だろうか?
山下氏は、「長期間にわたりお客さまとつながり、多様なデータを元にコミュニケーションできることだ」と言う。例えば、健診データや治療状況、入退院など、人生に関わる情報を共有しているのは、保険会社ならではの利点だ。ライフステージの全般にわたって、長い目で顧客に寄り添ったサービスを提供できる。
ただし、保険会社という立ち位置を活かし、顧客に寄り添うには、多様で複雑なデータを扱い、適切なコミュニケーションを行う必要がある。そのために組織されているのが、インシュアヘルス開発部なのだ。
保険業界の業績指標とは一線を画すミッション
山下氏は、インシュアヘルス開発部の役割を「デジタルとデータで価値を創造し、CXを起点とした新たなビジネスモデルへの変革」と定義する。特に、同社の提供価値である「健康応援」をデジタルで高度化するのが、CX開発グループのミッションだ。

具体的には、メールやアプリ、LINEなどのツールで、顧客と直接コミュニケーションをとり、健康行動を促進していくのが彼らのミッション。興味深いのは、山下氏、髙橋氏らが負う「健康行動数」という数値目標だ。CX開発グループは、2024年〜2026年までの3年間累計で「55万行動」の達成を目標数値としている。
「健康行動数」は顧客の健康行動を評価する、同社独自基準による指標だ。例えば歩行量でポイントがもらえるプログラム「ウォーキングチャレンジ」に12週基準を達成すると「1行動」として計算される。ある程度の継続が求められ、かなりのコミットメントが必要な指標であることがわかる。
しかも、施策の再現性がなければ「新たなビジネスモデルへの変革」という本来の目的は達成できない。「なぜ人は健康行動を起こすのか」「どうすれば顧客は行動を継続するのか」という、極めて深い顧客理解と再現可能な顧客コミュニケーション方法を見つけていくことも、グループのミッションには含まれる。それができて、はじめて簡単には模倣できない独自のビジネスモデルが完成する。ポイントキャンペーンを乱発して「健康行動数」だけ達成したとしても意味はないのだ。
一方で、契約数や売上、リード数など、一般的なマーケティングの指標は、グループの目標にはない。そのための難しさを、2人はこう語る。
「誰に、どのタイミングで、何を伝えるか、というマーケティングにおける根本的な『問い』に、答えていくことの難しさを感じる。人が意識を変え、健康行動を開始するきっかけは千差万別。一般的なマーケティングとは異なり、理論や技法は確立されていない。しかも、目の前にお客さまがいないデジタルなコミュニケーションで健康行動への動機付けをしていくのは、非常に難易度が高い。しかし、やりがいのあることだ。
行動科学をはじめ、さまざまな情報を参照しながら、お客さまとつながり、理解することが重要。顧客データ、CDP が大きな役割を担う」
新しい取り組みで、王道がない顧客とのコミュニケーションだからこそ、顧客データが重要な道標になるのだ。
1万7000人の健康改善をサポート
では、具体的にTreasure Data CDPをどのように活用しているのだろうか?
格納するデータは、保険の契約情報、Webサイトのアクセス履歴、「MYひまわり」アプリ内の行動データ、がんリスク検査をはじめ各種付帯サービスなど。前述の通り、データは非常に複雑で多岐にわたり、長期にわたり収集される。
同社では、これらのデータ活用に、GUIで顧客のセグメントを作成できるTreasure Data CDPの「オーディエンススタジオ」を活用。適切なターゲット、メッセージ、タイミングの仮説を立て、メールやLINE、アプリを通して、顧客に健康行動を促す。
例えば、健康診断の直後には「数値を改善したい」、結婚、出産などライフイベントの際には「家族のために健康になりたい」など、健康への意識が高まると考えられる。このタイミングで、前述の「ウォーキングチャレンジ」を促すメッセージを送れば、顧客の背中を強く押せるのではないか。そんな仮説を重ねて実行し、CDPと連携するBIツールで成果を可視化したうえで、検証・改善を繰り返していく。
結果、「健康☆チャレンジ!制度」に参加する顧客のうち、およそ13%に相当する1万7000人がチャレンジに成功、健康チャレンジ祝金を受け取るに至った。さらに、チャレンジ成功者は、成功していない顧客に比べて、入院率が約50%低いことがわかった。

「『健康☆チャレンジ!制度』には、健康に対する人の意識・行動を変え、それを継続させる力があることを、データとして確認できるようになってきた。インシュアヘルスの効果を実感しており、今後さらに加速させていきたい」(山下氏)。
データの民主化でリードタイムは1/30に
「外部ツールとの豊富なコネクタ、オーディエンススタジオをはじめ非エンジニアでも操作できるGUIツールなどが魅力。ほぼ毎日使っている」と、Treasure Data CDPを高く評価する髙橋氏。一方で「入社した時すでにTreasure Data CDPが導入され、社内にはデータが蓄積されていたが、十分に活用できていなかった」と、データエンジニアとして解決に苦心した2つの課題を振り返る。
ひとつめの課題は、データの分散だ。保険会社は金融機関であり、セキュリティが厳格に管理されている。当初はTreasure Data CDPに格納できるデータに制限があり、様々な部門、ツールにデータが散在していたという。
これでは、顧客データを統合するCDPとしての強みを活かせない。髙橋氏は社内ルールやデータ連携の問題点をひとつずつ解決し、Treasure Data CDPに顧客データを統合していった。
もう一つの課題は、非エンジニアのCDP活用が進まなかったことだ。前述のようにGUIを備えるオーディエンススタジオは、専門的な知識がなくても、データベースにアクセスできる仕組みだ。
しかし、CX開発グループの大半を占める非エンジニアのマーケターたちは、「抽出したデータが正しいかが不安」と言い、Treasure Data CDPに直接触れることをためらった。そのため、データベースの知識を持つ髙橋氏を中心に、CDP関連の作業が集中した。「データベース有識者に依頼→業務部門とターゲットの要件を擦り合わせ→データベース有識者がターゲットリストを作成→業務部門へ共有」(髙橋氏)という、長いプロセスが必要だったという。
髙橋氏は一人ひとりに伴走しながら、オーディエンススタジオに触れてもらうことから、状況を改善していった。簡単な操作で、知識がなくても正しいデータが取得できることを身をもって理解すると、データベースへの専門知識がなかった業務部門の担当も積極的に活用するようになった。
多くのメンバーが自ら、オーディエンススタジオでセグメントを作成するようになると、「ターゲットリスト作成の工数は1/10 に、リスト作成までのリードタイムは1/30になった」と髙橋氏。データ活用が民主化されたことで、スピーディに施策を実行できるようになった。また、多くのメンバーが課題意識を持って自らデータへアクセスすることで、成果への関心が高まり、検証・改善の精度も向上したという。
「デジタルなコミュニケーションで健康行動への動機付けをしていくのは非常に難しい。少しでも再現性のある顧客コミュニケーションを見出すためには、ターゲットリストの作成と配信、改善を繰り返していく必要があるので、リードタイムの短縮化は非常に重要」だと語る(髙橋氏)

「CDP World 2024」で感じた世界のトレンド
そんな髙橋氏は、2024年にトレジャーデータが主催する「CDP World 2024」に参加した。マーケティング、データ活用のトップランナーたちが、米国ラスベガスに集結し、議論するトレジャーデータのフラグシップイベントだ。
「キーノートや登壇した企業の事例から、世界のトレンドや方向性を認識し、それらについて深く考えることができた。またユーザー間での情報共有により、できていること・できていないことを含め、自分たちの立ち位置が明確になった」と髙橋氏は、その時の体験を振り返る。
2024年は、生成AIの話題が主流となった。「生成AIを使いこなすスキル、生成された内容を精査するスキルが重要」「顧客データから個別に件名や画像を生成するなど、AIによりクリエィティブもパーソナライズされていく」といったメッセージが、髙橋氏の印象的に残っているという。
「イベントへの参加により、CDPを使ってなにか成果を上げたいという思いも強くなりました」と髙橋氏は語る。
保険の新たなビジネスモデルを実現するために
今後は「MYひまわり」のアプリを中心に、CDPによるデータ活用をかけあわせ「お客さまにとって心地良い、自然な健康応援」(山下氏)を推進していく。
アプリが顧客に浸透し、活用が進めば、データの量は増大し、質的にも多様化していく。精緻なデータ活用に基づく施策の実行と検証が、同社のビジョンである「健康応援の高度化」を実現するはずだ。
また足下では、多様な顧客接点から得られるデータを全社的に統合し、コミュニケーションを連動させる「カスタマージャーニーオーケストレーション」の考え方を、実践していくという。多様なチャネルを通し、顧客の状態、行動に即した、より高度にパーソナライズされた施策を展開していく。
「インシュアヘルス」は保険会社にしかできない方法で、健康という代えがたい価値を提供する。顧客の健康リスクを軽減する仕組みは、保険のビジネスモデルを本質的に変える可能性がある。
それを支えるのが、多種多様な顧客データと、山下氏、髙橋氏はじめインシュアヘルス開発部の絶え間ない試行錯誤だ。トレジャーデータはデータ活用の専門家として、SOMPOひまわり生命保険の「インシュアヘルス」を強力にサポートしていく。